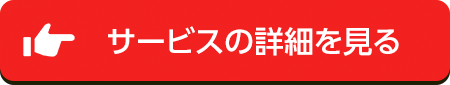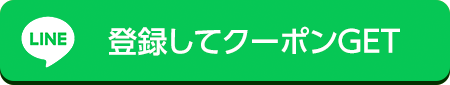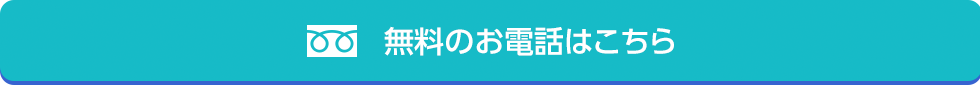トイレタンクからの水漏れ!異音!6つの原因箇所と修理方法を解説

トイレタンクからの水漏れ!異音!6つの原因箇所と修理方法を解説
【クラシアン】トイレの水漏れは、多くの場合タンクにその原因があります。特に、便器内に水がチョロチョロと流れ続けている、タンク内でずっと異音がしている、などの症状は、トイレのタンク内に原因がある水漏れ症状です。今回は、トイレタンクからの水漏れに対する適切な修理方法・修理費用の目安をご紹介します。
- トイレ
- タンク
- 修理
- 水漏れ
クラシアン編集部
最終更新日:
記事公開日:
目次
- 1. 【重要】まず最初に行うべき応急処置
- 2. トイレに水が流れる仕組みを理解しよう
- 3. トイレタンクの構造と各部品の役割
- 4. 動作の流れ
- 5. 【症状別診断】水漏れの原因を特定しよう
- 6. 音による症状分類と対処法
- 7. 【原因別】修理方法と難易度
- 8. 【自分で修理可能】ボールタップの不具合
- 9. 【自分で修理可能】フロートバルブの不具合
- 10. 【重要】DIY修理時の注意点
- 11. 【業者依頼推奨】オーバーフロー管の不具合
- 12. 【難易度中】給水管・接続部からの水漏れ
- 13. 【業者依頼推奨】タンク底部からの水漏れ
- 14. 【新規追加】予防・メンテナンス情報
- 15. 【判断基準】自分で修理 vs 業者依頼
- 16. 【安全上の注意】
- 17. 修理費用の目安
トイレタンクからの水漏れは、チョロチョロ音や異音の原因となり、放置すると水道代の無駄遣いや修理費用の増大につながります。陶器タンクの場合、多くは内部部品の劣化が原因で、適切な診断により自分で修理できるケースも多くあります。
トイレタンクからの水漏れは、多くの場合タンク内の部品に原因があります。特に、便器内に水がチョロチョロと流れ続けている、タンク内でずっと異音がしている、などの症状は、トイレのタンク内に原因がある水漏れ症状です。
このような症状が続くと、水道代の無駄遣いになるだけでなく、部品の劣化が進行して修理費用が高額になる可能性があります。早めの対処が重要です。
※この記事ではトイレの水を溜めておくタンク部分が陶器でできている「陶器タンク」についての症状・原因を取り上げています。
【重要】まず最初に行うべき応急処置

水漏れ発見時は、被害拡大防止のため「止水栓を閉める→タンク内の水を流し切る→水漏れ箇所の保護」の3ステップで応急処置を行いましょう。止水栓操作は安全な作業の基本です。
水漏れを発見したら、被害拡大を防ぐため以下の手順で応急処置を行いましょう。
- 止水栓を閉める(マイナスドライバーで右に回す)
止水栓は通常、トイレの横の壁か床にある銀色の金具です。手で回せるハンドル型かマイナスドライバー等使って回す内ネジ型があり、時計回りに回すと水が止まります。固い場合は無理をせず、少しずつ回してください。 - タンク内の水を流し切る
レバーを操作してタンク内の水を完全に空にします。これにより、作業中に水が溢れるのを防げます。 - タンクの外に水が漏れている場合は水漏れ箇所にタオルやバケツを設置
床が濡れると滑りやすくなり危険です。また、マンションの場合は階下への水漏れリスクもあるため、しっかりと水を受け止めましょう。
止水栓を閉めずに作業すると水が噴出し、家財をぬらす危険がありますので、慎重に作業を進めることが大切です。
トイレに水が流れる仕組みを理解しよう
トイレタンクは5つの主要部品(ボールタップ、フロートバルブ、オーバーフロー管、洗浄レバー、浮き球)が連動して動作します。各部品の役割を理解することで、水漏れの原因特定が容易になります。
トイレタンクの構造と各部品の役割
トイレタンクは複数の部品が連動して動作します。主要な部品とその役割を把握することで、水漏れ原因の特定が容易になります。
各部品の名前を覚えておくと、ホームセンターで部品を購入する際やメーカーに問い合わせる際に役立ちます。
- ボールタップ:給水を制御する弁(浮き球と連動)
この部品が故障すると、水が止まらなくなったり、給水されなくなったりします。 - フロートバルブ:排水を制御するゴム製の栓
便器への水の流れを調整する重要な部品です。劣化すると水が止まらなくなります。 - オーバーフロー管:水位が高くなりすぎた際の安全装置
万が一の水位異常時に、タンクから水が溢れるのを防ぐ役割があります。 - 洗浄レバー:フロートバルブを開閉するハンドル
私たちが普段操作する部分で、ここから鎖を通じて他の部品と連動しています。 - 浮き球:水位に応じて上下しボールタップを制御。
動作の流れ
- レバーを動かすと鎖でフロートバルブが持ち上がり、水が便器へ流れる
- 水位低下により浮き球が下がり、ボールタップが開いて給水開始。少し遅れて、フロートバルブが閉じる。
- 水位が規定値に達すると浮き球が上昇、ボールタップが閉じて給水停止
この一連の動作が正常に機能することで、トイレの水流が適切に管理されています。どこか一つでも不具合が生じると、水漏れや異音の原因となります。
【症状別診断】水漏れの原因を特定しよう

水漏れの症状は「継続的な音」「断続的な異音」「目に見える水漏れ」の3タイプに分類できます。音の種類や発生場所により、原因となる部品を特定し、適切な対処法を選択できます。
音による症状分類と対処法
チョロチョロ・ポタポタと継続的に音がする場合
このケースのポイント:水道代増加の主な原因となる症状です。フロートバルブかオーバーフロー管の不具合が考えられます。
- 可能性1:フロートバルブの不具合(排水口からの水漏れ)
この場合、便器内に水が流れ続けているため、水道代が上昇する原因となります。 - 可能性2:オーバーフロー管からの水漏れ
オーバーフロー管から水が流れていると、タンク内の水位が適切に保たれません。 - 可能性3:ボールタップの故障
オーバーフロー管に記載されている規定ラインを超えて水位が上昇し、オーバーフロー管上部から水が常時流れ込んでいる状態で、水道代が上昇する原因となります。 - 診断方法:タンクのフタを開けて水の流れを目視確認
懐中電灯やスマートフォンのライトを使用すると、タンク内の状況をより詳しく確認できます。
断続的に異音がする場合
このケースのポイント: 部品の動作不良が原因で、比較的簡単な調整で解決できることが多いです。
- 可能性:ボールタップの浮き球が引っかかっている
浮き球が壁面や他の部品に当たっていると、正常な動作ができなくなります。 - 診断方法:浮き球の動きを確認
手で軽く浮き球を動かしてみて、スムーズに動くかどうかチェックしましょう。
目に見える水漏れがある場合
このケースのポイント: 物理的な破損や劣化が原因で、部品交換が必要になることが多いです。
- タンク下部:接続部パッキンや手洗い連結管の劣化
床に水たまりができている場合は、この部分からの水漏れが疑われます。 - 給水管接続部:ナットの緩みやパッキン劣化
タンクの横や後ろから水が滲み出している場合に該当します。 - タンク本体:ひび割れや破損
陶器製のタンクにひびが入ると、そこから水が漏れることがあります。この場合は専門業者への依頼が必要です。
【原因別】修理方法と難易度
修理難易度は「自分で修理可能」「難易度中」「業者依頼推奨」の3段階に分類されます。ボールタップやフロートバルブの調整は比較的簡単ですが、オーバーフロー管やタンク取り外しが必要な作業は専門業者への依頼が安全です。
【自分で修理可能】ボールタップの不具合
症状:水が止まらない、異音が続く 原因:ボールタップ本体やパッキンの劣化、浮き球の引っかかり
修理手順
- 止水栓を閉める
- タンク内の水を流し切る
- 浮き球の位置を確認・調整
- 改善しない場合はボールタップを交換
ボールタップの交換作業は、工具としてモンキーレンチがあれば比較的簡単に行えます。ただし、部品の取り付け方向を間違えないよう注意が必要です。
注意点:節水目的でペットボトルをタンク内に入れると、浮き球の動作を妨げ故障の原因となります。節水グッズを使用する場合は、トイレメーカー推奨の製品を選びましょう。
【自分で修理可能】フロートバルブの不具合

症状:便器内への水漏れが止まらない 原因:フロートバルブの劣化、位置ずれ、鎖の絡まり
修理手順
- 止水栓を閉める
- フロートバルブの位置と鎖の状態を確認
- 異物除去や位置調整を実施
- 劣化している場合は交換(TOTO・LIXIL製で形状が異なるため要注意)
フロートバルブの交換時は、メーカーと型番を確認してから購入することが重要です。サイズが合わないと正常に機能しません。
【重要】DIY修理時の注意点
- オーバーフロー管の破損やタンクの損傷リスクあり
特に力を入れすぎると、陶器製のタンクが割れる可能性があります。 - 修理作業は自己責任となるため、不安な場合は専門業者へ依頼
重い部品の取り扱いに不安を感じる場合は無理をせず、家族や友人に手伝ってもらうことをおすすめします。
【業者依頼推奨】オーバーフロー管の不具合
症状:水が止まらない、オーバーフロー管からの水漏れ 原因:管の亀裂、取り付け部の隙間、管の破損
なぜ業者依頼が必要か
- タンクの取り外し作業が必要(重量があり1人では困難)
陶器製のタンクは重いので、力に自信がない方は一人で作業する場合は難しい可能性があります。 - 製品ごとに長さ・口径が異なり専門知識が必要
メーカーや製造年によって部品の規格が異なるため、適切な部品選びには専門知識が必要です。 - 製造中止品の場合、タンクごと交換が必要な場合がある
古いトイレの場合、部品の入手が困難で、システム全体の交換が必要になることがあります。
【難易度中】給水管・接続部からの水漏れ
原因:パッキンの劣化、ナットの緩み
修理方法:該当パッキンの交換、ナットの締め直し
作業手順
- 止水栓を閉める
- 水漏れ箇所にバケツ・タオルを設置
- ナットを外してパッキンを交換
- 必ず同じサイズ・形状のパッキンを使用
パッキンの交換は比較的簡単ですが、古いパッキンを完全に取り除いてから新しいものを取り付けることが重要です。古いパッキンの残骸があると、再び水漏れの原因となります。
【業者依頼推奨】タンク底部からの水漏れ
原因:便器とタンクの接続部パッキンの劣化
難易度が高い理由
- タンクの取り外しが必要
陶器製のタンクは重く、取り外し時に割れるリスクがあります。 - 破損・ケガのリスクが高い
重いタンクの取り扱いでケガをする可能性があります。 - 再組み立て時の調整が困難
水位やレバーの調整など、経験が必要な作業が含まれます。
【新規追加】予防・メンテナンス情報
定期的な点検(月1回の目視確認、3か月に1回の止水栓確認、年1回のパッキン点検)と適切な使用方法により、トイレタンクの故障を予防できます。部品交換の目安は5-15年です。
定期点検のポイント
- 月1回:タンク内の部品状態を目視確認
タンクの蓋を開けて、部品の位置や汚れ具合をチェックしましょう。 - 3か月に1回:止水栓の動作確認
止水栓が固着していないか、スムーズに動くかを確認します。 - 年1回:パッキン類の状態チェック
パッキンの劣化や変色がないか、定期的に確認することで早期発見ができます。
部品交換の目安
- ボールタップ・フロートバルブ:7-10年
使用頻度や水質により交換時期は前後しますが、目安として覚えておきましょう。 - パッキン類:5-7年
パッキンは消耗品です。定期的な交換でトラブルを予防できます。 - オーバーフロー管:10-15年
比較的長持ちする部品ですが、年数が経過したら点検を行いましょう。
故障を防ぐ日常的な注意点
- タンク内に異物を入れない
掃除用品やペットボトルなどを入れると、部品の動作を妨げます。 - 過度な節水グッズの使用を避ける
適切でない節水グッズは、かえって故障の原因となることがあります。 - 定期的な清掃とメンテナンス
月に一度程度、タンク内を軽く清掃することで、部品の寿命を延ばせます。
【判断基準】自分で修理 vs 業者依頼
工具不要の調整作業や簡単なパッキン交換は自分で修理可能です。一方、タンク取り外しが必要な作業、複数箇所の同時不具合、10年以上使用のトイレは業者依頼が推奨されます。
自分で修理できるケース
- 浮き球の位置調整
工具を使わずに手で調整できる簡単な作業です。 - 鎖の絡まり解消
鎖が絡まっている場合は、優しく解きほぐすだけで解決できます。 - フロートバルブの位置調整
位置がずれているだけなら、正しい位置に戻すだけで修理完了です。 - 簡単なパッキン交換
工具があれば、比較的簡単に交換できます。
業者依頼すべきケース
- オーバーフロー管の交換
専門技術と工具が必要で、DIYでは困難な作業です。 - タンクの取り外しが必要な作業
重量があり、一人では安全に作業できません。 - 複数箇所の同時不具合
原因が複雑で、専門知識が必要な場合があります。 - トイレ使用年数が10年以上
古いトイレは部品の入手が困難で、システム全体の見直しが必要な場合があります。
【安全上の注意】
作業に自信がない場合は無理をせず、専門業者に相談することをおすすめします。不適切な修理により、より大きな損害を招く可能性があります。
【追加】重い部品の取り扱いや力を必要とする作業では、安全を最優先に考えることが重要です。
修理費用の目安

クラシアンでは、トイレのタンク内やタンク周りの部品交換に「8,800円(税込)~+材料費」で対応しております。
年間70万件以上の水道トラブルに対応しているクラシアンは、トイレのタンク内部品の損傷や劣化などによる水漏れ修理も経験豊富。プロの目で判断し職人技で修理しますので、安心してご依頼ください。
お客様に安心してご利用いただけるよう、丁寧な説明と迅速な対応を心がけております。
【トイレの水が止まらない】原因と対策!まずは止水栓を閉めよう
トイレ・ウォシュレットのつまり・水漏れ修理交換のサービスと料金 | クラシアン
※この記事に含まれるデータは、公開時点のものであり、価格やサービス内容が変更されている場合があります。詳しくは最新の情報をご確認ください。
※本サービスが提供する情報の具体的な利用に関しては、利用者の責任において行っていただくものとします。